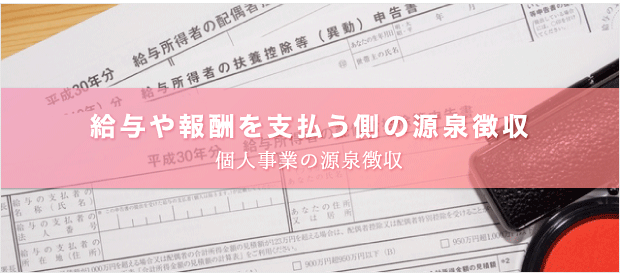「源泉徴収」とは、支払う給与や報酬などから、金額に応じた税金をあらかじめ差し引いて、事業主が納付する制度のこと。従業員に給与を支払っている場合は、源泉徴収が義務になります。外注先への報酬などに関しても、源泉徴収が必要になる場合があります。
この記事では、主に「源泉徴収をする側」の個人事業主に向けて説明をします。
目次
源泉徴収とは?
事業主は、従業員などに支払う給与から、あらかじめ金額に応じた税金を差し引いて、それを納付しなければなりません。この制度を「源泉徴収」と呼びます。源泉徴収が必要になるのは、主に以下の2つの場合です。
- 従業員や専従者(家族従業員)などへ給与を支払う場合
- 外注先などへ、特定の報酬や料金を支払う場合
源泉徴収で納付するのは「所得税」と「復興特別所得税」
現在、源泉徴収をして納付する税金は、「所得税」と「復興特別所得税」の2つ。これらをまとめて徴収し、納付します。「復興特別所得税」は、東日本大震災の復興のためにつくられた税金で、2037(令和19)年分までの所得に対して課せられることになっています。

個人事業主は源泉徴収を「する」ことも「される」こともある
従業員などを雇用する個人事業主は、基本的に源泉徴収を「する」ことが義務になります。対して、法人などと取引をして報酬を受け取る事業主は、源泉徴収を「される」こともあります。この記事では、主に源泉徴収を「する」側について説明します。
源泉徴収をする必要がある個人事業主
源泉徴収をする必要がある事業主を、「源泉徴収義務者」と呼びます。個人事業主の場合、従業員や専従者を1人でも雇って給与を支払っていれば、「源泉徴収義務者」に該当します。
「源泉徴収義務者」に該当する事業主は、外部に支払う報酬などの一部についても源泉徴収が必要になります。逆に「源泉徴収義務者」に該当しなければ、原則として源泉徴収をする必要はありません。
個人事業主が「源泉徴収義務者」に該当しない場合
従業員や専従者に給与を支払っている個人事業主は、必ず「源泉徴収義務者」に該当します。逆に、以下のいずれかに当てはまる事業主は「源泉徴収義務者」に該当しません。この場合、外部へ支払う報酬などについても、ほぼ全ての場合で源泉徴収は不要になります。
- 従業員や専従者がいない
- 常時2人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)だけに給与を支払っている
- 税理士などだけに報酬・料金等を支払っている
そもそも従業員などを雇わず、ひとりで事業を行っている場合、「源泉徴収義務者」には該当しません。確定申告を税理士に委託している場合も、ほかに給与などの支払いがなければ、その報酬は源泉徴収をしなくてOKです。
「源泉徴収義務者」になったら
従業員などを雇って給与を支払うことになったら、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出して「源泉徴収義務者」となったことを届け出ます。なお、開業の時点から従業員などがいる場合は、「開業届」にその旨を記入して提出すればOKです。
届出が済んだら、実際に給与や報酬などに対して源泉徴収を行っていきます。このとき、源泉徴収をする税額の計算方法は、「従業員などの給与から源泉徴収をする場合」と「外注先への報酬などから源泉徴収をする場合」で以下のように異なります。
| 源泉徴収の対象 | 源泉徴収額の計算方法 |
|---|---|
| 従業員などの給与 | 給与額と扶養家族の人数を「税額表」に照らし合わせて算出 |
| 外注先への報酬など | 「支払金額 × 10.21%」を基本として算出 |
それぞれの計算方法について、以下で詳しく説明します。
従業員などの給与から源泉徴収をする場合
従業員などの給与から源泉徴収をする税額は、社会保険料等を差し引いた給与額と扶養家族の人数をもとに、「税額表」で照らし合わせて決定します。その上で、年末に「年末調整」を行い、源泉徴収をした税額の過不足を精算することになります。
源泉徴収をする税額は「税額表」で決定する
従業員などの給与から源泉徴収をする税額は、「税額表」を参照して決定します。月給・日給・賞与などといった給与の種類によって、それぞれ異なる「税額表」が用意されています。
「税額表」では、縦軸と横軸がそれぞれ「給与の範囲」と「扶養家族の人数」になっており、それらが交わるところに源泉徴収すべき税額が記載されています。
扶養家族は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で把握する
税額を計算する際には、あらかじめ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に記入してもらい、扶養家族の人数を確認しておく必要があります。従業員は、毎年はじめの給与を受け取る前日までに、この申告書を事業主に提出する義務があります。
年末調整で一年分の過不足を精算する
給与支払いの際に源泉徴収をする税額は、「税額表」に基づいて決定する「おおよその金額」です。そのため、一年分の給与を支払ったら「年末調整」を行い、源泉徴収をした税額の合計と正しい「年税額」との過不足を精算します。
外注先への報酬などから源泉徴収をする場合
従業員などへ給与を支払って「源泉徴収義務者」になったら、外注先などへ支払う報酬や料金についても源泉徴収が必要になる場合があります。源泉徴収が必要かどうかは、報酬などの内容や、支払う相手によって異なります。
源泉徴収が必要な報酬・料金など
「源泉徴収義務者」が源泉徴収をしなくてはならない報酬などは、主に以下のようなものです。なお「源泉徴収義務者」の場合でも、支払う相手が法人(会社など)であれば、原則として源泉徴収は不要です。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人への報酬や料金
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人への報酬や料金
源泉徴収をする税額は「支払金額 × 10.21%」が基本
外注先へ支払う報酬などから源泉徴収をする場合、税額は「支払金額の10.21%」が基本になります。ただし、100万円を超える部分に関しては、以下のように計算方法が異なります。また、一部の報酬などに関しては、計算方法が異なる場合もあります。
| 支払い金額 | 源泉徴収をする税額の計算方法 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | 100万円 × 10.21% + ( 支払金額 – 100万円 ) × 20.42% |
すこし複雑な計算式になりますが、報酬のうち「100万円を超える部分」には倍の税率がかかるということです。
源泉徴収をした税額の納付方法
源泉徴収をした所得税などは、対象となる給与や報酬の支払いの翌月10日までに納付します。所定の「納付書」を添えて銀行や税務署で納付するほかに、「e-Tax」を利用してインターネット上で納付を行うこともできます。
従業員などに「月給」を支払う事業主の場合、基本的には毎月納付の手続きが必要になります。しかし、それでは手間がかかるうえ、納付忘れなどのリスクも高くなるため、条件を満たせる事業主は「源泉所得税の納期の特例」を利用することをおすすめします。
「源泉所得税の納期の特例」で納付を年2回にまとめられる
給与を支払う相手(従業員など)が常に10人未満の事業主は、「源泉所得税の納期の特例」を利用して、給与などから源泉徴収をした税額の納付を、年2回にまとめることができます。この場合の納付スケジュールは、以下のようになります。
| 1月~6月までに源泉徴収した税額 | その年の7月10日までに納付 |
|---|---|
| 7月~12月までに源泉徴収した税額 | 翌年の1月20日までに納付 |
この特例を利用する場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。申請書を提出すれば、翌月分の源泉徴収から特例が適用されます。

ただし、この特例の対象となるのは「従業員への給与」や「税理士などへの報酬」などから源泉徴収をした税額のみです。その他の外注先への報酬などから源泉徴収をした分はまとめることができず、通常通り翌月10日までの納付が必要になります。
まとめ – 給与や報酬を支払う側の源泉徴収
事業主は、従業員や専従者に支払う給与から、金額に応じた税金をあらかじめ差し引いて、それを納付しなければなりません。この制度を「源泉徴収」と呼びます。主に以下のような場合に、源泉徴収をする必要があります。
- 従業員や専従者(家族従業員)などへ給与を支払う場合
- 外注先などへ、特定の報酬や料金を支払う場合
源泉徴収をしなくていい個人事業主の条件
以下のいずれかに当てはまる個人事業主は、外注先へ報酬などを支払うときでも、ほぼ全ての場合で源泉徴収をする必要がありません。
- 従業員や専従者がいない
- 常時2人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)だけに給与を支払っている
- 税理士などだけに報酬・料金等を支払っている
源泉徴収をする必要があるのは「源泉徴収義務者」だけ
従業員や専従者に給与を支払っている事業主は、「源泉徴収義務者」に該当します。「源泉徴収義務者」は、外注先などへ支払う一部の報酬・料金についても、源泉徴収が義務になります。
源泉徴収をした税金の納付は「翌月10日まで」が基本
源泉徴収で給与から差し引いた税金は、その給与を支払った翌月の10日までに納付するのが基本です。しかし、従業員が10人未満の事業主は「納期の特例」を利用して、年2回の納付にまとめることもできます。