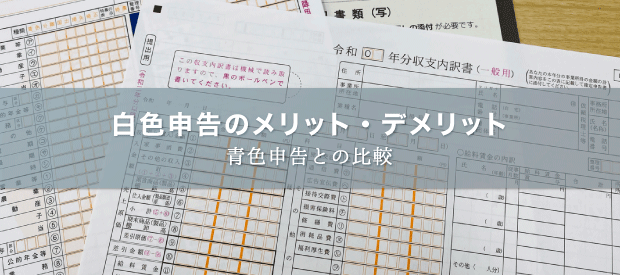確定申告の方法には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。本記事では、白色申告のメリット・デメリットについて、青色申告と比較しながら紹介しています。
目次
白色申告のメリット・デメリット
青色申告と比較した場合の、白色申告のメリット・デメリットは以下の通りです。白色申告のデメリットは、青色申告で受けられる節税特典がないことです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
青色申告よりも簡単
|
節税につながる特典がない
|
メリット① 税務署への事前申請が不要
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
| 事前申請不要 | 「青色申告承認申請書」を事前に提出* |
*一度提出するだけでよい
白色申告で確定申告をする場合、事前申請は不要です。一方で、青色申告で確定申告をするには、事前に税務署へ申請書を提出し、青色申告での申告を認められる必要があります。その手続を完了していない人は、自動的に白色申告になります。
メリット② 帳簿づけが簡単
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
以下の記帳方法が認められている(併用可能)
|
以下のように記帳方法が分かれる
|
白色申告では、簡易簿記という記帳方法で帳簿づけをします。さらに、白色申告者は、簡易な方法による記載も認められています。この2つを掛け合わせることで、ラクに帳簿づけを済ませることができます。
ただし青色申告の10万円控除においても、簡易簿記での帳簿づけは認められています。また、クラウド会計ソフトを使えば、初心者でも簡単に、複式簿記で帳簿づけが可能です。白色申告と青色申告における、帳簿づけの難易度の差は、それほど大きくはありません。
用語解説
| 簡易簿記 (単式簿記) |
家計簿やお小遣い帳のような記帳方法 |
|---|---|
| 簡易な方法による記載 | 細かな記載を省略できる方法(白色申告者のみ) 例 : 少額な現金売上は、日々の合計金額をまとめて記載してよい |
| 複式簿記 | 取引の両面(原因と結果)を記録する記帳方法 |
メリット③ 決算書の記入項目が少ない
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
収支内訳書(決算書)
|
青色申告決算書
|
白色申告者は「収支内訳書」という決算書を作成して、確定申告で提出します。収支内訳書は全2ページで構成されており、青色申告者が作成する決算書(青色申告決算書)よりも、記入項目が少ないです。
一方、青色申告で55万円・65万円の控除を受けるには、全4ページの決算書を作成する必要があります。ただ、クラウド会計ソフトを使えば、決算書は簡単に作成できます。クラウド会計ソフトでは、日々の取引を記録していれば、決算書のほとんどは自動的に作成されます。
用語解説
| 決算 | 個人事業主においては、帳簿をもとに以下の書類(決算書)を作成すること ・収支内訳書(白色申告の場合) ・青色申告決算書(青色申告の場合) |
|---|---|
| 決算とは – 確定申告の3つのステップ | |
| 貸借対照表 | ・決算書の一種で、決算時の財政状態を示すもの ・青色申告決算書の4ページ目にある ・55万円&65万円控除の場合のみ、作成が義務づけられている |
デメリット① 青色申告特別控除が適用できない
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
| 特別控除がない | 10万円 or 55万円 or 65万円の特別控除 |
白色申告に特別控除はありません。これが、青色申告に劣る大きなデメリットです。青色申告の場合、クリアする要件に応じて上表の特別控除が適用できます。
青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除は、下図のとおり差し引かれるものです。

このように、青色申告特別控除を差し引いた金額に、税率を掛け、所得税を求めます。そのため、収入が高ければ高いほど、節税額は大きくなっていきます。下記の記事では、ざっくりと節税額を比べています。
【所得300万円】税額比較 – 白色申告と青色申告(65万円控除)
【所得500万円】税額比較 – 白色申告と青色申告(65万円控除)
用語解説
| 控除 | ある金額から一定の金額を差し引くこと(主に所得控除や特別控除が該当) 以下のように、控除が多いほど、節税に繋がる |
|---|---|
| 所得税の算出 – 控除が多い場合と少ない場合の比較 |
デメリット② 青色のように赤字繰越できない
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
| ごく一部のみ繰越可能 | 事業で生じた赤字額を、翌年以降に繰越すことができる*(最大3年間) |
*前年に赤字を繰戻すことで、払いすぎた税金を受け取ることも可能
白色申告では、基本的に赤字の繰越しができません。例外的に、以下の場合の赤字・損失は繰越しができますが、該当者はそれほど多くありません。
- その年ごとに変動が大きい所得(印税や原稿料、作曲料など)における損失
- 災害による事業用資産の損失
青色申告における赤字の繰越しは、事業で生じた赤字の金額を、翌年以降3年間に渡って、各年の黒字所得から差し引くことができる、というものです。以下の例では、1~3年目は「所得税を納付しなくてよい」ということになります。

デメリット③ 少額減価償却資産の特例が利用できない
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
| 少額減価償却資産の特例が利用できない →10万円以上のものは減価償却をする |
少額減価償却資産の特例が利用できる →10万円以上30万円未満のものは一括で経費に計上できる* |
*年間で合計300万円まで
「少額減価償却資産の特例」は、ざっくり言うと「10万円以上30万円未満のものを買ったときの費用は、全額をまとめてその年の経費にしてよい」というものです。
白色申告では、この特例を利用できません。そのため、取得価額が10万円以上の減価償却資産を取得したら、「減価償却」をすることになります。
一方、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」が適用できます(2022年3月31日まで)。この特例を利用すれば、取得価額30万円未満のものであれば、一括でその年の経費に計上することが可能です。
用語解説
| 取得価額 | 品物購入から実際に使い始めるまでに直接かかった費用の合計額 品物の代金・購入手数料・送料・関税などを含めた金額 |
|---|---|
| 減価償却資産 | 高価な事業用資産のうち、時の経過によって価値が下がっていくもの パソコン・カメラ・建物・空調設備・自動車など |
| 減価償却 | 帳簿の上で減価償却資産の資産価値を減らし、経費計上すること 例:高価なパソコンを購入したとき →まずは資産に計上し、指定年数の4年で少しずつ経費にしていく |
デメリット④ 専従者控除の金額に上限がある
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
| ・「専従者」がいれば「事業専従者控除」を利用できる ・控除額に上限あり |
・「専従者」へ支払った給与が「必要経費」に計上できる ・全額を経費に計上できる* |
*支払給与額が妥当であると認められる場合
白色申告では、事業専従者がいれば、「事業専従者控除」という控除を利用することができます。ただし、控除額の上限は以下のように定められています。
- 事業専従者が配偶者(妻や夫)の場合…………最高86万円まで
- 事業専従者が配偶者以外の場合………………最高50万円まで
青色申告では、事業専従者控除は利用できません。しかし、事業専従者へ支払った給与の全額を、必要経費に計上することができます。
用語解説
| 事業専従者 | 以下の3つの条件全てを満たす人のことを指す
|
|---|
*場合によっては、事業に従事できる期間の2分の1を超えていればよい(青色申告のみ)
デメリット⑤ 貸倒引当金の繰入れ
| 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|
|
|
白色申告では、一括評価によって貸倒引当金の繰入れをすることができません。ただし、個別評価で貸倒引当金の繰入れをすることは認められています。
用語解説
| 貸倒引当金 | 取引先から回収できなくなりそうな債権(売掛金や未収金など)の一部のこと。これを必要経費に計上できる |
|---|---|
| 貸倒引当金の繰入れ | ・貸倒引当金を計上すること ・計上した金額は「貸倒引当金繰入」と呼ばれる |
| 個別評価 | 「貸倒引当金」の金額を決める評価方法の1つ 繰入れの要件は厳しいが、繰入れできる金額が多い |
| 一括評価 | 「貸倒引当金」の金額を決める評価方法の1つ 繰入れの要件はゆるいが、繰入れできる金額が少ない |
まとめ
| 白色申告 | 青色申告 | ||
|---|---|---|---|
| 10万円控除 | 55万円控除 65万円控除 |
||
| 事前申請 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 帳簿づけ | 簡単 | 簡単 | 難しい |
| 決算書 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 (貸借対照表は不要) |
青色申告決算書 |
| 事業専従者給与 | 控除できる金額に 上限あり |
全額を経費に 算入できる* |
全額を経費に 算入できる* |
| 赤字の繰越し | ごく一部のみ 利用可能 |
翌年以降3年間 利用可能 |
翌年以降3年間 利用可能 |
*「労務の対価として相当であると認められる金額」との定めあり
白色申告は帳簿づけから確定申告まで、簡単に終えることができます。しかし、これまで示してきたとおり、青色申告で認められるような節税特典はありません。
「わざわざ青色申告の申請を出すのが面倒」「所得がそれほど高くなく、節税できる金額が少ない」という人には、白色申告が適当でしょう。
ただ、クラウド会計ソフトによって青色申告の帳簿づけ・申告書類作成のハードルは下がっていますから、会計ソフトの利用予定がある方は青色申告を検討してみて下さい。